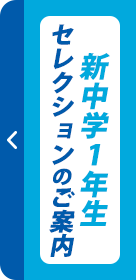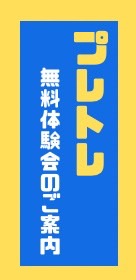いつも朝イチの警備解除が担当なんだが、今日はすでに警備が解除されてた。
誰がきてるんだと気になり、事務所に入ったが、誰もいない。
朝一誰か仕事してそのまま出て行ったんだろう。
くそ、負けた(笑)
最近YouTubeで、東大の先生が運動について発信してるチャンネルにハマっている。
歳はおそらく、60〜70くらいの先生方だが、
運動を科学的に分析し、見ている人に伝える
ってのが主旨みたいで、まじ面白い。
昨日見たのは、100メートル走の話で、
ある走者を分析したら、
大腿四頭筋(腿の前の筋肉)と、ハムストリングス(腿の裏側)の筋肉のバランスで、
足の回転運動が速くなってる。
今まで鍛えてなかったハムストリングスを鍛えよう
で、どんどんタイムが向上し、
それが、1990年代に入ると、
とてつもなく速いカールルイスが出てきて、
また回転運動の話だが、どうやら足全体がスムーズに回っている。
これは、もっと違う部分が作用してると分析し、
体幹が重要だと気づき、体幹の中で大切な大腰筋という深部筋をどう鍛えるか?
という課題にぶつかり、、、
車で見てるんで、そこで止まってるが、
とにかく、
ねちっこくて、難しい話もされて訳わからない事もあるが、
とても論理的で、話の筋に意味があって、興味をそそられる。
運動理論を深く学びたいわけではなく、知識として少しあれば良いくらいかなという感覚だが、
それよりも、物事の考え方・捉え方の方にどちらかと言えば興味があり、
そんな観点で切り口作りながら、理論というのを構築してるんだな
とかを学んでるつもりだが、
その動画コンテンツの色んな回で
これからの運動は脳っていうのをしきりに言ってて、
なんかその辺も妙に刺さる。
3年生にものすごいロングスローを投げる子がいるんだが(笑)
身体が大きいわけでもなく、どちらかと言えば身体つきは華奢。
筋力という観点で見ると、みんなと変わらないのに、
なぜ?
を考えた時に、それはスキルを獲得してるかどうかに行き着く。
投げるコツっていうのを彼なりに分かってると思うんだが、
運動は、コツを掴むがとても重要だと思う。
ボールを蹴るコツもあれば、ボールを止めるコツもあるし、リフティングもコツが必要で、
それは、究極で言うと、
イメージと動きを一致させる
になると思うが、
イメージと動きを一致させるには、試行錯誤が必要で、
その試行錯誤には、
なんとなくやり続けるではなく、考えながらというのが必要。
動画の中でも、
反復練習は無駄ってバサっと切ってたが、
質をどう高めていくか
は、必ず考えるという脳を使う力が必要で、
ずーっとその原点を辿ってみると、
つまりは、やらされるのはダメで、自分でやる
が必要ってとこに行き着く。
理解力があるない。もしくは、やる気があるない。
もっと言うと、理解しようとする。上手くなりたい。
こんなんが、その下のもっとがっちりとした土台としてないといけないと思うが、
やっぱり試行錯誤をどう繰り返していけるのか。それをコツコツと。意味あるものとして。
科学がどんどん進化して、サッカーで言えば、戦術がどんどん進化していく中で、
なんでも進化していくのは当たり前だから、
頭が追いついていかないといけないのも当たり前になると思う。
運動は学習だ。学習には忍耐が必要だ。
正解かどうかは分からないが、
俺はそういった意味でも、
勉強する。学業に励むは、きっと効果があって、
学ぶとは何か?
が楽しくなれば、より一層運動という分野でもそれが活かされ、成長に繋がると思っている。
学ぼう。試行錯誤しよう。そして、コツコツ継続しよう。
それやれれば、大外れしない未来が待ってると思う。

頭を使え(笑)